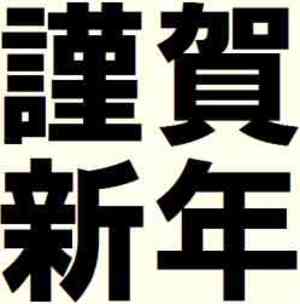ホットトイズはもはや終焉を迎えた。
香港限定から始まり、豆魚雷の独占流通ルート、MMS DX二番煎じ商法
さらには
2010年12月24日(金)の招待されない三国人はお断りします会
バブルのバカ騒ぎか会員制クラブまがいか
12月25日(土)の18000万円以上買わない貧乏人はお断りします会
そして
12月26日(日)日本の豚2500匹よ!
中国の旗の下ホットトイズにひれ伏して足を舐める会
このような限定パーティやメンバー制、特別待遇の皮を被った消費者の区分けは
発展途上のメーカーにおける促進剤としてしばしば行われる。
会社としては消費者の格差意識を利用して高級な企業評価を得たり
招待した客が各所で吹聴することによって容易に企業価値が上がるだろう
という目論見だが容易さは往々にして裏目に出る。
時に差別された者と優待された者同士の対立や古参消費者の反感を招き
その後に多大な影響を与える。
ホットトイズと同じような過程は
バンダイなど玩具メーカー以外にもオークリーやナイキなど多くの企業が経てきた。
こうしたメーカーは盲目に商品を買い漁るコレクターや転売ヤーの性質を存分に理解し利用しており
商品も一般消費者が延々とコレクションしやすい分かりやすいシリーズを備えている。
転売によって価格が定価以上に吊り上がることは、無条件で商品を購入する信者を増やす意味でも重要なファクターであり
メーカーは単に在庫を懸念して生産しないのではなく、こうした市場価値の上昇を期待している。
会員制、優待制、株主待遇、限定商法やプレミアム商法や手直し色直しの焼き直し商法による
際限のないブランド価値底上げの繰り返しが企業の本質を圧迫し企業価値を低下させていく。
こうしてホットトイズの勘違い行脚はいよいよ頂点に向かう。

返信する